アドラーの勇気づけって何?
居場所がない感じがする
人を信頼できない

・アドラー心理学の勇気づけの意味
・「勇気づけ」を日常生活の中に取り入れた方法
アドラー心理学は
嫌われる勇気
でご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
アドラー心理学とは、オーストリアの心理学者アルフレッド・アドラーによって提唱された心理学の理論です。
・勇気づけ
・目的論
・共同体感覚
・劣等感と優越性の追求
・自己決定性
などさまざまな用語があります。

なんか難しそう…
難しそうなワードが多いですが、今回はアドラー心理学をより身近に感じられるように、「勇気づけ」を「ありのままの自分を受け入れること」と絡めて
【自分に対する勇気づけの具体的な実践方法】
✔「できていること」に目を向ける
✔他人との比較をやめる
✔失敗を受け入れ、成長の糧にする
【勇気づけをするときに大切なポイント】
✔自分自身の感情・考えを尊重する
✔結果ではなく努力を認める
✔「べき思考」を手放す
【「勇気づけ」と「褒めること」の違い】
について紹介していきます。
勇気づけとは、社会の中で他者と協力して生きることを決心すること

勇気づけには、「自分に対する勇気づけ」と「他者に対する勇気づけ」があります。
今回は、自分に対する勇気づけについて紹介します。
自分自身に対する勇気づけとは…
・自分の人生を自分自身で引き受けること
・他者と協力して生きることを決心すること
だといわれています。

勇気づけといっても、褒めたり期待することとは違う点に注意!
アドラーは、人は常に何らかの課題や問題に直面しており、それらを乗り越えるためには「勇気」が必要だと考えました。
このことから、「勇気づけ」という概念が生まれたようです。
「自分に対する勇気づけ」をすることが自分を受け入れることにつながる
自分に対する勇気づけ:具体的な実践方法
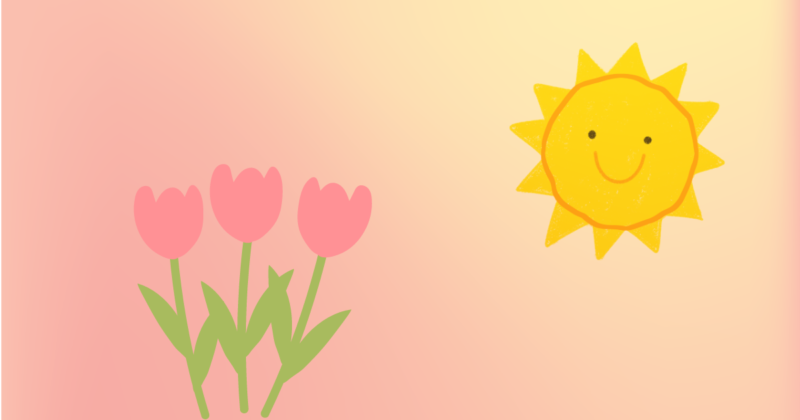
勇気づけの具体例について3つ紹介します。
「できていること」に目を向ける
たとえば、今日の自分が昨日の自分よりも少しでも進歩していることに目を向けます。
「できていること」に目を向けてみると「自分が成長していること」も認識できるかもしれません。
「完璧である必要はない」という意識を持ち、自分が達成した小さな成果を肯定的に評価してみましょう。
ここで大切なのは、「勝ち」「負け」にこだわらないことです。
これは次に紹介する、他人との比較をやめるにも関係してくる事柄です。
完璧であることを評価するよりも、取り組んだこと自体を評価する
他人との比較をやめる
アドラーは、他者との比較を「劣等感」の原因と捉え、それが自信を損なうと考えました。
自分を他人と比べるのではなく、
過去の自分と比べること
が、自己成長の鍵となります。
「他の人はもっと成功している」と感じる瞬間があったとしても、その思考を切り替え、
「自分はどう進歩しているか?」
を問いかけるようにしてみましょう。
また、SNS上で他人の成功を見ると自己評価が低下する原因になることがあります。
必要に応じてSNSを控え、他人と自分を無理に比較しないよう心がけることも大切です。
他者ではなく、過去の自分と比べる
失敗を受け入れ、成長の糧にする
アドラー心理学では、失敗は単に終わりではなく、成長の機会と捉えます。
失敗を恐れるあまり行動を起こせないと、自分に対する信頼も低下してしまいませんか?
大切なのは、失敗をどう受け止め、それを学びに変えるかです。
失敗した原因を冷静に分析し、次にどのように改善できるかを考えてみましょう。
ここで重要なのは、失敗を批判的に捉えず、未来に向けた学びと考えることです。
失敗をしたからといって自分の価値が下がるわけではありません。

誰でも失敗することはあるよね
失敗を恐れない心を育てていきましょう。
失敗は成長のもと
勇気づけをするときに大切なポイント

上記で紹介した勇気づけを実践する際に、意識しておきたいポイントについて紹介します。
自分自身の感情・考えを尊重する
自分の気持ちや考えを否定せず、共感的に受け止めることを意識しましょう。

頑張ったのにうまくいかなかった…
やる気出ないや…(そう感じるのは当然だよね)
結果ではなく努力を認める
アドラー心理学では、成功や結果よりも努力やプロセスを評価することが重要とされています。
失敗を責めるのではなく、挑戦したこと自体を褒める姿勢が、自己成長を促します。

うまくいかなかったかもしれないけど、一生懸命取り組んだことが素晴らしい!!
「べき思考」を手放す
「こうあるべき」という考えに縛られず、今の自分をそのまま受け入れることが大切です。
・成功するべき
・周りの人よりも頑張るべき
などの「べき思考」は、自分を責めることにもつながってしまいます。

「べき」に囚われず、自分がどうしたいのか考えてみよう
「勇気づけ」と「褒めること」の違い

先ほども少し紹介しましたが、「勇気づけ」と「褒める」ことには大きな違いがあります。
・失敗した状況でも受け入れる
・ありのままの自分を受け入れる
・「やったこと」自体を評価する
・期待していることを達成できた
・上から下への関係性の中で生まれる
今回は、「自分に対する勇気づけ」をテーマに紹介しましたが、「他者に対する勇気づけ」の場合、このような違いに注目してみると分かりやすいかもしれません。
「勇気づけ」は無条件の評価
基本の積み重ねが自信につながる
今回は、アドラー心理学の「勇気づけ」ともに、自分を受け入れる方法をテーマにお送りしました。
実は私自身、アドラー心理学の考え方にあまり馴染めず、共感できないと感じたことがありました。
(以前アドラーの本を読んだときは、ポジティブ過ぎてついていけない感じがしました)
ですが、今回改めてアドラー心理学の本を読んでみて、少し印象が変わりました。
勇気づけの実践方法については、言ってしまえば「基本的なこと」なのかもしれません。
しかし、その「基本的なこと」こそが、人間にとって大切なことなのだと改めて感じました。
最後に

アドラー心理学について、もっと知りたい!
という方向けにおすすめの本を紹介しているので、ぜひご覧ください。
参考文献&おすすめの本
本記事を書くにあたって参考にした本と、おすすめの本の紹介です。
岩井俊憲(2023)アドラー流気にしないヒント,三笠書房.
アドラー心理学の考えが、実生活の悩みへの対処法と合わせて書かれています。
巻末には、アドラー心理学の用語についても分かりやすく紹介されています。
アドラー心理学を日常生活に当てはめて学びたい
向後千春 (2017)幸せな劣等感アドラー心理学<実践編>,小学館.
アドラー心理学の基本的な知識が身につきます。
Q&Aで素朴な疑問について解決できるのも嬉しいポイントです。
アドラー心理学の基本的な知識を身につけたい
永藤かおる(2018)悩みが消える「勇気」の心理学アドラー超入門,ディスカヴァー・トゥエンティワン.
図やイラストが多く、文章だけではピンとこない言葉でも、分かりやすく書かれています。
勇気づけについても詳しく触れられています。
勇気づけについて、もっと詳しく知りたい
ぜひ、アドラー心理学の考え方を、実生活に取り入れてみてください!
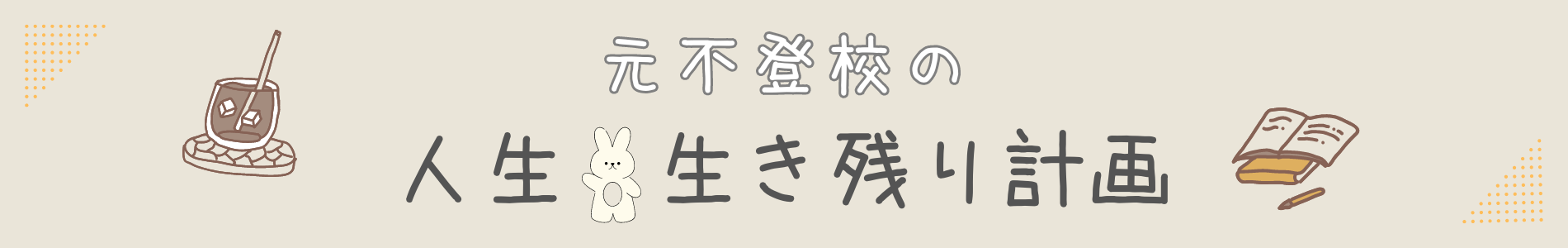
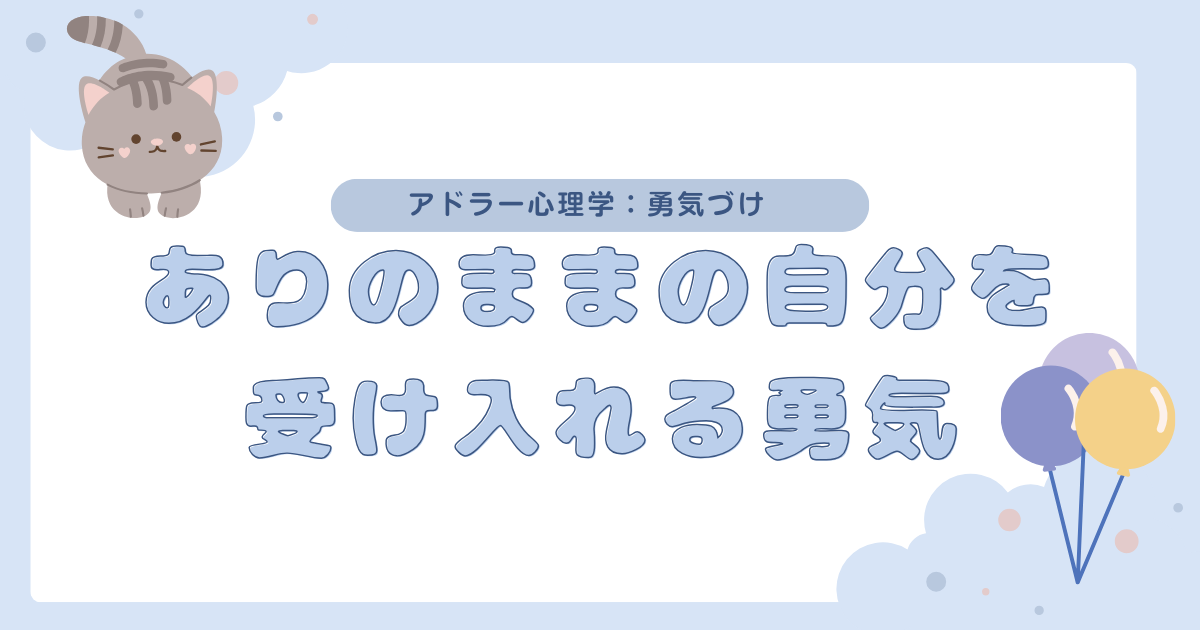
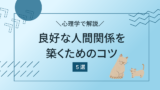
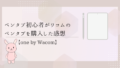
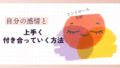
コメント